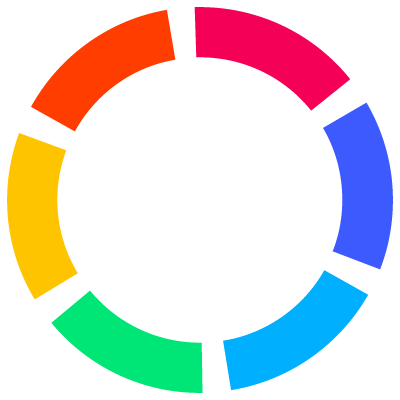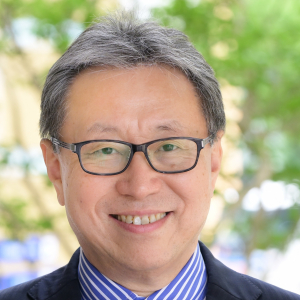シンポジウム,デモ展示など特別イベントに関しての情報を掲載しております。
タイムテーブルに関しましては、こちらのページにて詳細をご覧いただけます。
[企画セッション1]
KIBME/ITE Joint Session
企画:大会実行委員会
-
Chairperson greeting from ITE(TBA)
-
Title:TBA

Keio University
Hideo Saito
-
Title:TBA

Hanyang University
Jong-Il Park
-
Break time(Chairperson change)
-
Chairperson greeting from KIBME(Jong-Il Park(Hanyang University))
-
Title:TBA

EMX
Sung Gyu Lee
-
Title:TBA

Nagoya University
Chihiro Tsutake
[企画セッション2]企業におけるAI開発の足跡と展望
企画:メディア工学研究委員会
深層学習の出現以降,AI技術は目覚ましいスピードで革新が進み,産業界においてもAIの実用が日進月歩で拡大しています.
しかし,開発から実用に至るまでの道程は平坦ではなく,各企業はさまざまな障壁を乗り越えながら,実用に資する技術を生み出してきました.
そこで本企画セッションでは,放送・電機・通信の分野におけるAI開発の先導者として活躍されている方々をお招きし,企業におけるAI開発の足跡と今後の展望について,実用例の紹介を交えながらご講演いただきます.
8月27日(水)13:00~14:40
会場B
座長:望月貴裕(NHK)
-
開会
-
放送メディアを支えるAI技術の変遷と可能性
人工知能(AI)という用語が70年前に誕生して以来,AI技術は目覚ましく発展し,近年はテキストや画像を作り出す革新的な生成AIが登場した.NHK放送技術研究所は1960年代から放送への応用を目指して,画像認識,音声認識,音声合成,自然言語処理などAIの研究開発に取り組み,これまでに映像自動要約や生字幕制作,音声自動読み上げ,日英機械翻訳などの技術を実用化し,コンテンツ制作の効率化や視聴者サービスの拡充に貢献してきた.本講演では,放送メディアを支えるAI技術の変遷を振り返り,技術的な要点を整理して,今後の可能性を展望する.

NHK
今井 亨
-
三菱電機AI『Maisart』による画像処理技術とその実用化事例
三菱電機では,「機器・エッジをスマート化し,人と共に進化し続けるAI」を目標とし,これまで映像認識技術やモデルのコンパクト化技術,それを活用した映像監視システム,外観検査システムなど様々な画像処理技術を開発,実用化してきた.本招待講演では,画像処理に関わる三菱電機の研究開発事例ならびに実用化事例について報告する.特に,エッジ機器に載せるためのコンパクト化や学習データの問題など,実用化に向けた課題を中心に紹介する.
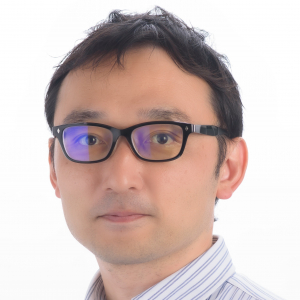
三菱電機
伊谷裕介
-
通信業界における生成AI活用事例と今後の展望
本講演では,急速に進化する生成AIのトレンドと通信業界における具体的な活用事例について紹介する.カスタマーサポートにおける顧客応対から,ネットワーク運用業務の効率化,映像認識に至るまで多数の適用先が期待される一方で,ハルシネーション等の生成AI特有の課題に伴う導入障壁やリスクについても触れ,対処法について紹介するとともに,今後の生成AI活用の展望についても解説する.

KDDI総合研究所
南川敦宣
-
閉会
[企画セッション3]ローカル5Gの研究・利活用最前線
企画:放送技術研究委員会
ローカル5Gはどのような分野で活用が出来るのか?ローカル5Gを利用することで何ができるのか?ローカル5Gに関する研究,利活用に取り組んでいる専門家の方々から講演をいただき,ローカル5Gの持つポテンシャルや将来像について理解を深めていただくことを目的とした企画セッションです.
8月27日(水)15:30~17:40
会場A
座長:岡田 実(奈良先端大)
-
開会
-
アナログRoFを用いたローカル5G ミリ波SFNにおける4K映像伝送
動画視聴などのコンテンツが充実し,モバイル通信に置いてユーザあたりの通信容量拡大の需要が高まっている.大容量無線通信の実現方法としてミリ波の活用が挙げられ,第5世代移動通信システム (5G)およびローカル5Gでも新たにミリ波の割り当てが行われた.伝搬損失や回折損失が大きいミリ波の面的な展開には,基地局から複数のアンテナを張り出し一つのエリアを形成するSFN (Single Frequency Network)構成が有効である.本稿では,アナログRoF (Radio over Fiber)を用いてローカル5GでSFNを構成した4K映像伝送実験を紹介する.

NTTアクセスサービスシステム研究所
○菅 瑞紀・髙橋雄太・山本泰義・依岡寛人・坪井秀幸・藤田隆史
-
ローカル5GでのLiDAR点群データリアルタイム伝送によるロボット制御応用
本報告では,ブレインレスの移動ロボット群をMulti-access Edge Computing (MEC)からローカル5Gを介して集約的にリアルタイム制御するMEC集約型の移動ロボット制御技術について述べる.移動ロボットの「頭脳」にあたる機能をMECに集約し,移動ロボット本体側は「動く」機能に絞ることで,移動ロボット群の全体最適制御を可能にし,トータルのシステムコストを低減する.移動ロボット搭載のLiDAR点群データをローカル5Gでリアルタイム伝送を行い,移動制御のための自己位置推定処理をMECで行う.東芝の総合研究所と府中事業所にローカル5Gを設置し,走行実証を行ったので結果について報告する.

東芝
○旦代智哉・大野健一・今井一博・大屋靖男
-
ローカル5Gが拓く新たな放送・映像伝送の世界: 実験から見えてきたその可能性
ローカル5Gネットワークは,放送・映像伝送分野で大きな可能性を秘めています.
上りのデータ伝送に高帯域を確保し,免許制周波数による安定した品質と通信の安全性を実現します.
また,災害時の緊急通信ツールとして地域の情報発信を支援し,衛星回線との連携で孤立化を防止する等,放送・映像伝送に最適なソリューションとなっています.
これらの特長を実施経験を基にご紹介します.
NECネッツエスアイ
藤澤隆行
-
ローカル5Gを活用した8K遠隔手術支援(指導)臨床試験
世界初の臨床試験結果をもとに,8K超高精細映像とローカル5G通信を融合した遠隔手術支援の取り組みを紹介します.8K映像がもたらす圧倒的な実物感と,電子ズームによる腹腔鏡の俯瞰視野は,手術の精度と安全性を高めるとともに,若手術者への質の高い指導を可能にします.さらに,ローカル5Gの低遅延・高帯域通信により,リアルタイムで安定した遠隔支援環境を構築.次世代医療の可能性と,通信インフラや制度設計など社会実装に向けた課題について展望します.

NHK財団
島本 洋
-
閉会
[企画セッション4]8K超高精細映像技術の医療応用最前線
企画:大会実行委員会
医療現場においてもテクノロジーの進化が日々加速している.
中でも8Kスーパーハイビジョン技術の高解像度・広色域・高フレームレート等の有用性を医療に応用する動きが期待されている.
現行のハイビジョンである2Kと比較し,16倍の高解像度や映像とは思えない色合い映し出すことのできる広色域を持つ8Kスーパーハイビジョンは,医療分野の先進技術として医師の手術や診断の応用への取り組みが行われている.これまでの8K超高精細映像技術の医療への応用事例について講演いただく.
8月28日(木)10:00-12:10
会場A
座長:村上由紀夫(日大)
-
開会
-
【基調講演】8K超高精細映像技術の医療への応用
スーパーハイビジョンともよばれる8Kは,次世代放送メディアとしてNHKによって提案・開発された画素数7,680×4,320の超高臨場感テレビである.この画素数はハイビジョン(2K)の16倍に相当することから,8Kは超高精細テレビであるともいえる.メディカル・イメージング・コンソーシアムでは,2013年より8K映像技術を内視鏡手術に応用する研究を進め,従来の2Kの内視鏡手術カメラでは鮮明な映像として見ることが困難であった体内の微小な血管や神経,臓器の境界部が新開発の8K内視鏡手術カメラではクリアに捉えられることが確認された.本講演では8K映像技術とその医療応用について,それらの開発の経緯も含めて報告する.

ニューヨーク州立ストーニーブルック大
谷岡健吉
-
8K超高精細映像技術の腹腔鏡手術システムへの応用
我々は8K超高精細映像技術の医療応用を2009年より開始し,8Kカメラの大幅な小型軽量化を経て,2017年に8K腹腔鏡手術システムの実用化を達成した.デジタルズーム機能を備え,術者にとって適した視野で微細な血管や神経,膜組織等を確認しながらの手術が可能になった.また,8Kの膨大なデータ量に対応した8K映像レコーダーを開発し,医局での閲覧や編集,学会等での外部発表が容易になった.さらに,8K対応のエンコーダやデコーダと組み合わせ,8K腹腔鏡手術の映像をリアルタイムに別の病院へ伝送し,複数の医師でサポートするような環境を構築できるようになった.今後の周辺技術やネットワーク環境の充実により,更なる医療の発展を期待している.

エア・ウォーター/帝京大
山下紘正
-
8K超高精細映像技術の歯科医療応用の基礎検討と将来展望
発表者は外来,病棟,訪問診療など様々な場で歯科診療に従事しており,有病者,入院患者などに対し歯科治療を行っている.日々の診療に従事する中で気づいた課題の解決方法を模索する中で8K超高精細・超高臨場感映像技術の歯科分野での活用に強い関心を持ち,その技術の歯科医療への応用の検討を続けてきた.
肉眼で見えにくかった対象物が8Kの活用によって鮮明に見えるようになることで歯科医師の正確な診断や高度な遠隔情報の共有が可能となり,住んでいる地域に関係なく安全で適切かつ円滑な歯科医療を提供できると考えている.本企画セッションでは,8Kによる基礎的な実験結果とその歯科応用の今後の展望について述べる.
東京科学大
國澤輝子
-
8Kカメラ開発の現状と医療展開の可能性
高解像度・広色域・高フレームレートを特徴とする8K技術は,手術支援や遠隔診療など多岐にわたる医療応用が期待されている.本稿では既存の8Kカメラがどのように医療応用できるかを考察し,生体イメージング分野での活用可能性について検討していく.
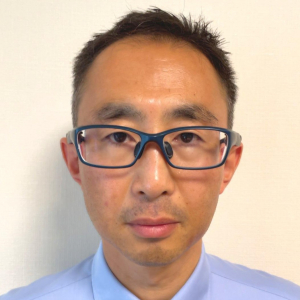
アストロデザイン
真鍋吉仁
-
閉会
[企画セッション5]放送100年 技術の発達と放送メディア
企画:大会実行委員会
NHK放送文化研究所は,2024年3月10日「放送100年 技術の発達と放送メディア」と題する『放送メディア研究』第17号を刊行した.(https://www.nhk.or.jp/bunken/book/media/17.html)
出版に際してのコメントは以下のとおり.
—————————————
ラジオ放送の誕生,テレビ放送の開始,白黒テレビからカラーテレビへの移行,衛星放送の開始,テレビの高品質化,放送のデジタル化など,放送をめぐるさまざまな変化の背景には,技術の進歩が存在していた.2025年の放送開始100年を前に,放送技術の発達に焦点を当て,それが放送をどう変えたか,さらには社会に何をもたらしたかを特集する.
—————————————-
この特集では,放送の創成期から技術開発の未来像まで,時々の研究・開発の様子や取り組みなどが,幅広い視点で紹介されている.
放送開始から100年の節目を捉え,本特集の刊行にあたられた編集担当の方,執筆を担当した技術者の方々にその内容について講演いただくことで,放送技術の進展を振り返るとともに,将来の放送メディアを展望する.
8月28日(木)14:40-17:40
会場A
座長:森本 聡(フジテレビ)
-
開会挨拶
-
「放送100年 技術の発達と放送メディア」刊行にあたって
NHK放送文化研究所(文研)では,放送開始から100年を機に,メディアの歴史を振り返る冊子『放送メディア研究』第17号を刊行しました.「放送100年 技術の発達と放送メディア」と題し,放送技術の発達に焦点を当て,それが放送をどう変えたか,さらには社会に何をもたらしたかについての特集です.編集に際しては,メディア研究者に限らず,技術開発の当事者にも執筆して頂く「書き手の多様性」を考慮.最終的にはメディア研究者8名,技術研究者5名,文研研究員5名と,様々な視点から書かれた一冊になりました.今回はその全体像について,紹介する予定です.

NHK放送文化研究所
柳憲一郎
-
テレビの発達と基礎研究 ~ NHKに基礎研究所がなぜできたか?またその結果は? ~
今やNHKに基礎研究所があったことを知る人も少なくなっていると思われるが,本講演では1965年に設立されたNHK放送科学基礎研究所(基礎研)の設立経緯を放送の黎明期までさかのぼって振り返る.さらに講演者の所属した同研究所視聴科学研究室での研究内容とその成果を述べ,1984年に放送技術研究所と統合された後もさまざまに展開された研究成果の今日の姿,社会へのインパクトを示す.とりわけ世界を席巻しているAI技術の本質的な部分が放送科学基礎研究所で行われた研究により発見された脳の情報処理原理「ネオコグニトロン」に基づくことを述べる.また今後どのような方向性で研究開発を進めるべきかについても述べてみたい.

前NHK財団
伊藤崇之
-
衛星放送の構想,研究,開発から実現へ
1966年の衛星放送研究開始から,日本は世界に先駆けて,衛星放送の実現に取り組み,実用化の面でも成功を収めた.これは,いち早く衛星の将来性に気付いた先見の明,キーとなる技術である受信コンバーターなどの研究に取り組んだこと,その結果として小型受信アンテナの使用が可能になったこと,さらには,番組面,サービス開発面での貢献が大きい.本稿では,初期段階の放送衛星開発の苦難の歴史や,BS-3以降,筆者が研究で取り組んできた放送衛星搭載用アンテナについても述べる.

放送衛星システム
正源和義
-
デジタル放送の開発経緯
2000年に衛星デジタル放送が開始され,2003年には地上デジタル放送がスタートした.当時はテレビ放送以外には実現できなかった動画サービスも,現在ではネットを用いたサービスが主流となっている.今回,地上デジタル放送の開発に焦点を当て,アナログからデジタルへの転換に際し,圧縮や伝送技術の進展や日本独自の要件を整理する.また,家庭向けハイビジョン放送と現在の動画サービスにもつながるワンセグの階層伝送等,技術方式を紹介する.

蔵前工業会
黒田 徹
-
4K・8K 究極の二次元テレビへの挑戦
今年は日本におけるラジオ放送開始の開始を起点とした「放送100年」であるが,それと同じ時期にBairdや高柳建次郎により,テレビジョンの初期のデモがなされている.その後,テレビジョンはSDTV,HDTV,そして4K・8Kと進化して今に至っている.本講演ではこのうち,4K・8Kに焦点を当て,「究極の二次元テレビ」を目標になされた映像フォーマットの開発と国際標準化の経緯について概観する.
なお,本講演はNHK放送文化研究所が2024年3月10日に発行した『放送メディア研究』第17号の記事「放送100年 技術の発達と放送メディア」に掲載された内容に基づいている.
リーダー電子
菅原正幸
-
ネット時代の放送技術
インターネットの普及をきっかけに,人々のメディアへの接し方が多様になり,放送局はインターネット上でメディアサービスの提供を開始した.この背景の中,放送が担う役割を維持,発展させていくための技術テーマを考えると,放送波,あるいは放送と通信の連携・融合という物理的な伝送手段の概念から前進し,人々の生活の中でのメディア体験,メッセージ・情報の伝達手段を考慮しなければならない.本講演では,放送・テレビによるメディア体験を振り返るとともに,NHK放送技術研究所が将来のメディア体験の実現に向けて提案する「Webベース放送メディア」を中心に紹介する.

NHKデジタルセンター
藤澤 寛
-
質疑・閉会挨拶
【フェロー記念講演】
映像情報メディア学会には,テレビジョンを含む映像情報メディアに関する学術および産業分野の発展・普及・振興あるいは本学会事業の発展に対して,特に貢献が顕著と認められる会員に高い尊敬と深い感謝の意を表するための制度として,フェロー会員の認定制度があります.本企画では,新たにフェローの称号が贈呈されました皆様を講師としてお招きし,映像情報メディア技術の発展に寄与した業績をご講演いただきます.
【招待講演】
-
22B-1[招待講演]歩行動作における足底運動の解析とその応用
片足支持では「足関節の捻れ問題」が生じ,高齢者などでは足関節の捻じれが原因で関節痛や運動習慣の低下を招く.この問題を抑制し,効率的な歩行を実現するために,接地面を外側に傾けることが有効である.片足立位時の足底の動作評価に基づいて最適な傾斜角度を判定する方法と,接地面の外傾化が歩行に及ぼす影響について紹介する.また,登山路に応じた歩行技術の獲得を支援することを目的として,荷重遷移マップを用いた足底運動の可視化手法についても紹介する.さらに,得られた研究成果の他スポーツへの応用について議論する.

日大
嶌田 聡