| ここで問題を整理すると、1は色成分が失われること、2はカメラで動くものを撮ると画像がボケる、すなわち、高域成分が失われること。3、4も高域成分が失われることです。したがって、画面が暗くなる現象は次の2点に集約されます。
(A)色成分が失われると画面が暗くなる。
この現象は、表示系の電気入力(電圧)と光出力(輝度)が比例しないことが原因です。 |
|||||
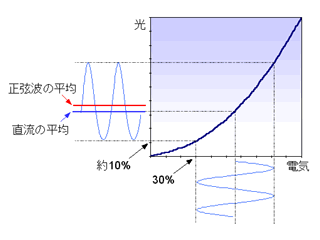
図1 表示系の光電変換特性 |
|||||
図1に表示系(特にブラウン管)の光電変換特性を示します。この特性は、HDTVの場合、ITU-R
BT.709[1]によって、次のように定められています。光レベル(L)、電気レベル(V)とも基準白ピークを1に正規化して、両者の関係は次式で表されます。
テレビ放送系では、受信機のコストを安価にするため、カメラ側で図1の逆特性をもつ非線形処理を行っています。これを、「ガンマ補正」と呼びます。このため、電気信号は輝度に対して線形ではありません。このことによって、表題のような現象が生じます。 はじめに、輝度信号(Y)のマトリックスを係数を丸めた形で、次のように仮定します。 Y=0.3R+0.6G+0.1B 図をご覧下さい。この式から、100%の赤(R)は30%の輝度をもつはずですが、モノクロ表示すると、約10%になってしまいます。このことから、カラー表示をモノクロ表示に切り換えると、輝度が低下することが分かります。では、残りの20%は?。これは、色信号が輝度信号の一部を運んでいるのです。 次に、電気信号で正弦波を入力します。光出力では、正の半サイクルが伸び、負の半サイクルが縮みます。その結果、光出力の平均レベルは直流レベルより高くなります。正弦波を高域成分と考えれば、高域成分が失われることによって、輝度が低下することが分かります。 |
|||||
| 以上、画像処理上の重要な現象をまとめると、
(1)色信号とはいえ、この中に輝度成分も含まれます。
このことは、光の領域で、色から輝度にクロストークが生じていること意味します。これは、色信号の彩度に依存し、彩度が高ければ高いほど顕著に現れます。彩度がなければクロストークは生じません。というわけで、あまり色信号を痛めるような信号処理は禁物です。 |