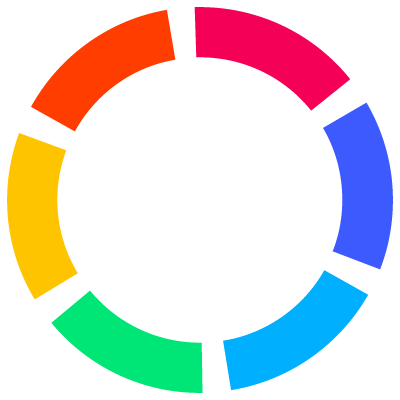シンポジウム,デモ展示など特別イベントに関しての情報を掲載しております。
タイムテーブルに関しましては、こちらのページにて詳細をご覧いただけます。
[企画セッション1]KIBME/ITE Joint Session(講演原稿:英語)
企画:大会実行委員会
8月28日(水)13:00~14:40
会場C
Chairperson:
Jeongchang Kim(Korea Maritime and Ocean Univ.)
Go Irie(Tokyo Univ. of Science)
-
Chairperson greeting

Tokyo University of Science
Go Irie
-
Overview of Deep Learning-Based Supervised and Self-Supervised Image Denoising Methods with an Introduction of a New Self-Supervised Method
We provide an overview of supervised and self-supervised image denoising techniques, as well as a new self-supervised method based on deep learning. Image denoising has seen significant advancements with the rise of deep learning, much like other image restoration and computer vision problems. Through the development of new deep network architectures, training strategies, and datasets, supervised deep learning methods now outperform traditional non-learning approaches by up to 10dB in some cases. However, creating well-registered, noisy-clean image pairs for training is challenging, and thus, there is a limited number of practical training images. Additionally, a denoiser trained with a specific dataset may not perform well for images with different properties. Consequently, there is a growing demand for self-supervised training methods that do not rely on external training sets. In this presentation, we will first offer an overview of key supervised denoising techniques and datasets. We will then examine self-supervised denoising methods that can remove noise without the need for external datasets, introduce our new self-supervised method, and discuss potential future directions.

Seoul National University
Nam Ik Cho
-
Personalized Cheering Message Application Using Sound Communication in Concert Environments ~ Developing an App to Enhance Real-Time Interaction in Live Performance ~
We propose a personalized cheer app using index communication in audio band.
Since there is almost no music signal in the frequency range between 16kHz and 20kHz,
we use this frequency band to transmit index signals to idol group fans’ cell phones for cheering.
Each pre-made idol cheer screen automatically changes according to this index signal.
This cheering app is currently implemented for Android phones.
University of Seoul
Chan-hwi Park・○Young-gil Kim
-
Break time(Chairperson change)
-
Chairperson greeting

Korea Maritime and Ocean University
Jeongchang Kim
-
Electrochromic Display Devices with Metallosupramolecular Polymers
With the worldwide interest in SDGs, electrochromic (EC) devices have received attention again to the application to smart windows (electrically tint-controlled glass for efficient sunshade) by utilizing the nonvolatile properties. However, as the present smart windows are not accepted by general users, because they do not satisfy the EC performance and price the users demand. As the EC properties greatly depend on the EC materials, the development of new EC materials is essential. This presentation introduces metallosupramolecular polymers (MSPs) as new EC materials bearing both excellent EC properties and processability, compared with the conventional EC materials including Tungsten oxide and viologen. MSPs are a branch of coordination polymers and were synthesized by simple complexation of metal ions and organic ligands. MSPs exhibited reversible EC changes between the colored and colorless states by electrochemical redox of the metal ions. As the color of an MSP is caused by the metal-to-ligand charge transfer (MLCT) absorption of the complex moieties, the combination of the metal and the organic ligand provided various colored polymers including purple, blue, red, green, yellow, and black. By optimizing the device structure, the EC devices with MSPs were driven at 0.8 V and showed high durability for the repeated color changes more than 100,000 cycles.
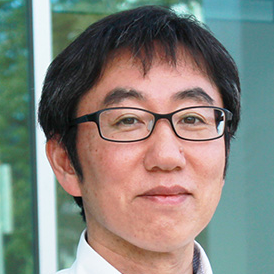
National Institute for Materials Science
Masayoshi Higuchi
-
Image Registration based Joint Space Narrowing Quantification for Rheumatoid Arthritis
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease primarily affecting peripheral synovial joints. Conventional Radiography plays acritical role in the diagnosis and monitoring of RA. Limited by the current spatial resolution of radiographic imaging, joint space narrowing (JSN) progression of RA can be less than one pixel per year. Insensitive monitoring of JSN can hinder the radiologist/rheumatologist from making aproper and timely clinical judgment. We propose a novel and sensitive method called an image registration-based JSN progression quantification framework, which can quantify sub-pixel level JSN progression in the early RA. We utilize a frequency domain analysis method and a CNN-based rigid registration network to verify the performance of the proposed framework, respectively. Our experiments demonstrated that the image registration-based JSN progression quantification framework exhibits greater advantages and potential in terms of accuracy and sensitivity compared to two other mainstream frameworks for joint space quantification, namely margin detection-based joint space width (JSW) quantification and machine learning classification-based scoring. We are optimistic that our proposed method will significantly contribute to the automatic quantification of JSN progression in RA.
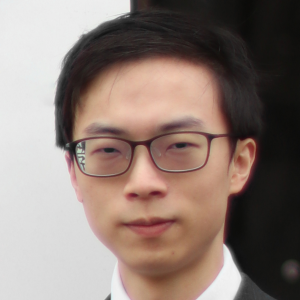
Tokyo Institute of Technology
○Yafei Ou

Hokkaido University
Haolin Wang・Tamotsu Kamishima・Masayuki Ikebe
[企画セッション2]MoIP放送技術
企画:映像情報メディア学会北海道支部
毎年11月に幕張メッセで開催される国内放送業界向け最大級イベントInter BEEでは2018年から複数社合同企画展示としてMedia over IP(以降MoIP)技術にフォーカスしたIP PAVILIONという動態デモンストレーションに取り組んでいます.2022年は35社,2023年は34社が参加.今年はINTER BEE DX x IP PAVILIONと名称リニューアルしAI,Cloud,Security要素を加えた展示検討を進めています.この度本会よりMoIP放送技術について登壇する機会を頂きました.本セッションでは,まず放送設備オールIP化の実例を紹介し,続いてIPPAVILION 2023メンバーにてMoIP放送技術を5つのパートに分けてご紹介します.
8月29日(木)14:15~17:30
会場A
座長:金子健二(NHK札幌)
-
放送設備のIP化の実際
テレビ北海道では,2024年1月にマスターのIP化,4月と6月にニューススタジオ,制作スタジオをIP化し,オールIP放送局として運用を開始した.IPシステム整備の経験から導入するために特に考慮すべき点や,導入して分かったIPのメリットについて報告する.また,オールIPシステムの一つとして運用している,バーチャルマスターオペレーターによる運用の効率化についても紹介する.
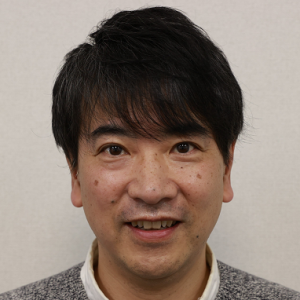
テレビ北海道
高橋康二
-
MoIP放送編(SDIとIP比較)
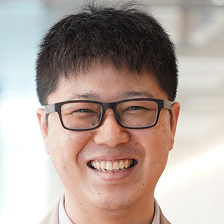
ソニーマーケティング
中尾 誉
-
MoIP PTP編(BBとPTP比較)

リーダー電子
野﨑稔雄
-
休憩
-
MoIPネットワーク編(Media面)

東京エレクトロンデバイス
松岡 諒
-
MoIPネットワーク編(制御面)

エイチ・シー・ネットワークス
濵田悟史
-
MoIP監視編

Zabbix Japan
長谷川幹人
[企画セッション3]映像情報メディアの将来を語る
企画:大会実行委員会
映像技術やネットワーク技術の急速な進化により,ドローンやスマートフォンを活用して, 世界中のあらゆる様子をリアルタイムで伝えることが可能になりました.また,生成AIを用いた映像や音声の合成は,映像コンテンツの生成や大量のデザイン案の提案など,ビジネスの効率化から新しい価値提供にまで活用の機会が広がっています.一方で,SNS利用に伴うプライバシー侵害のリスクや本物と見間違えるような映像によるフェイクニュースの懸念など映像に関わる課題も増えてきており,映像情報を安心かつ安全に扱えることが求められています.
そこで, 本企画セッションでは,東京大学,NHK,KDDI,日立より第一人者をお招きし,映像情報メディアの最新動向と,課題の解決に向けた今後の方向性について講演とパネルディスカッションを行います.
※本セッションは予稿はございません.
8月29日(木)15:30-17:30
会場B
座長:樋口晴彦(日立) 学会総務理事
■登壇者
司会 樋口晴彦(日立) 学会総務理事
パネリスト① 相澤清晴(東京大学 教授)
パネリスト② 神田菊文(NHK放送技術研究所 所長)
パネリスト③ 小西 聡(KDDI総合研究所 副所長兼先端技術研究所長)
パネリスト④ 鈴木教洋(日立総合計画研究所 取締役会長)
■形式:ショートプレゼン(10分程度)+パネルディスカッション
・自己紹介+映像情報メディア分野の取組みや今後の展望を各人より10分程度ショートプレゼン
・Q1:生成AIのインパクト
・Q2:映像情報メディア分野の研究開発で日本が世界に伍していくには
・Q3:映像情報メディア学会への期待
・Q4:(最後に)若い研究者へのメッセージ
[企画セッション4]防災・減災のための放送技術
企画:放送技術研究委員会
近年,ゲリラ豪雨,地震など災害の頻発が社会問題化しており,防災,減災に対する取り組みがますます重要になってきています.こうした状況を踏まえ,防災に関する放送局の取り組みや,防災のための放送技術の研究開発動向について,被災地域で実際に対応された放送局の経験や,防災に向けた様々な技術動向について,様々な立場の専門家から講演をいただき,今後の防災・減災に放送が果たす役割について,より深い理解を深めることを目的とした企画セッションを開催します.
8月30日(金)9:50-12:00
会場A
座長:岡田 実(奈良先端大)
-
開会
-
令和6年能登半島地震における中継局及び避難所対応について
2024年1月1日の元日に発生した令和6年能登半島地震は最大震度7を記録し,奥能登地域を中心に甚大な被害をもたらした.道路や電力・水道・通信等のライフラインが寸断され,テレビやラジオ放送を行っているNHKの中継局についても被害が生じた.半島の先端で発生した地震は地理的な要因もあり,復旧作業は難航を極めた.今回,被災地に放送を届けるためにNHKが行った中継局での復旧作業や,避難所での活動について報告する.

NHK金沢
阿部雅夫
-
地域の防災・減災のために放送局ができること ~ 地上デジタル放送波を活用した¨IPDC 災害情報伝達手段¨の普及に向けて~
自然災害が激甚化する中,より確実に住民へ災害情報を伝える手段の整備が地方自治体に求められている.これを実現する一つが「地上デジタル放送波を活用したIPDC災害情報伝達手段」だ.
テレビ局の放送用電波のごく一部を活用し,自治体が発出した災害情報を住民に伝えるもので,読売テレビでは社会貢献の一環として,日本で初めて2022年から実施している.テレビ局の中継局を活用できるため,自治体にとっては防災行政無線に比べ,安価で確実な情報伝達手段になり得る.
住民は家のテレビ用アンテナ端子に接続した戸別受信機から情報を得られるため,風雨の音などによる聞き逃しのリスクも軽減できる.
住民の生命を守るために,地域のためにテレビ局はどのような協力ができるのか?
その一つが「地デジIPDC災害情報伝達」ではないかと考える.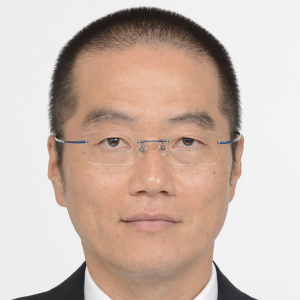
讀賣テレビ
杉山 亮
-
「みちびき」災害・危機管理通報を活用した被災対応FMラジオ放送システム実証 ~ FMラジオ放送を活用した防災・減災への取組み ~
ラジオ放送は,手持ちのラジオ受信機で容易にかつ,気軽に情報を得ることが可能なメディアとして利用されている.またラジオ放送は日常だけでなく災害時での情報伝達における利便性が非常に高い.
そこで,災害時等においてラジオ放送ネットワークの一部が途絶した場合でも,準天頂衛星システム「みちびき」から配信される,災害・危機管理通報サービスを活用して自動放送により災危情報を途切れなく提供できるFMラジオ放送システムの構築を目指し内閣府のみちびき実証事業として実験を行った.
山口放送/山口大大学院
惠良勝治
-
災害報道におけるAR/VR技術
災害報道というと「いち早く必要な人に必要な情報を」という役割が強いものの,一方でその場でしか取得できないデータをもとに次の世代に語り継いでいきたいという長期的な要求もあります.本講演では,防災意識を高めることを目的とした最新のAR/VR技術による「語り継ぎ」の取り組み事例を紹介します.
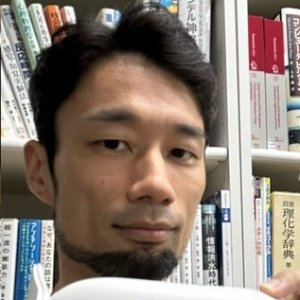
NHK技研
川喜田裕之
-
閉会
[企画セッション5]ウェットプロセスによる光学特性変換デバイスの開発
企画:情報ディスプレイ研究委員会
近年,光学特性を変換するデバイスにおいて,これまでのスパッタリングや蒸着などの物理プロセスに対して,基盤材料のインク・塗料化,それを用いた好適なウェットプロセス技術の開発など,化学プロセス的な研究開発事例が増えてきている.本企画セッションでは,ウェットプロセスによる光学特性変換デバイスの開発と題して,産総研で開発を進めているエレクトロクロミック調光デバイス,液晶調光デバイスの事例紹介,ならびに近赤外線をコントロールする新技術に関して話題提供を行って頂く.
8月30日(金)13:00-16:00
会場B
座長:樋口昌芳(物材機構),田嶌一樹(産総研)
-
開会のあいさつ
-
印刷型エレクトロクロミック調光材料の開発と社会実装研究
住宅や自動車の窓は外を見るために使われるが,室内には窓を通して多くの太陽光が入り込む.そのため,室内が過度に暖められることになり空調負荷が増加する一因となっている.ビルや住宅では,ブラインドやカーテンなどの機械的な手段で熱を遮断することができるが,自動車では安全上の理由から一般的に困難である.そのため,気候,時間,季節など場面に応じて光学特性を可変することで取り込む太陽光を調整できる「調光技術」に期待が寄せられている.本講演では,窓から流入する太陽光を制御するための様々な調光技術と講演者らが開発した機能性ナノ粒子分散インクを用いた印刷型調光フィルムの開発について紹介する.

産業技術総合研究所
田嶌一樹
-
車載向け印刷型エレクトロクロミック調光フィルムの開発
近年,自動車では大型サンルーフやパノラマルーフの搭載がトレンドとなっている.これは,開放感など意匠的な理由のほか,電動化による床下へのバッテリー設置や,空気抵抗低減のためのルーフ位置降下によって圧迫される頭上空間を,ガラス化によって内装トリムレスとして拡大しようという背景を併せ持っている.一方で,ルーフのガラス化が進むと,乗員が眩しさや頭部の暑さを感じやすく,また,特に電動車においては空調調効率向上が課題となっている.そこで,本公演では講演者らが開発中の熱マネジメントにも寄与できる印刷型調光フィルムの開発経緯,製品化へ向けた最新の開発状況,現状の製造方法などについて紹介する.

林テレンプ
福井理晃
-
印刷型エレクトロクロミック調光デバイス用封止技術の開発
産総研では機能性ナノ粒子分散インクを用いた印刷型エレクトロクロミック調光デバイスの研究開発を進めている.当該デバイスの社会実装においては,使用環境に対する耐久性を満足する必要があり,この耐久性に寄与する要因の一つが接着剤等を用いた封止技術になる.当グループでは,接着関連の様々な研究開発も行っており,接着・接合に対する幅広い知見を有する.本講演では,当グループが推進している接着関連技術開発,ならびにデバイス用封止技術の開発に関して紹介する.

産業技術総合研究所
島本一正
-
休憩
-
感温タイプ調光材の実用化に向けた研究開発
気温に応じて日射透過率を制御する実用的な調光材料を開発した.これは液晶と高分子がメゾスケールで相分離した複合構造で,液晶とモノマーの混合原料を透明基板に薄く挟みUV光硬化するだけで,自己組織化形成する.調光は透明/白濁で行われるが,従来の同様タイプと違い,この調光で室内に入る日射の25%以上を制御し,夏冬の冷暖房負荷削減に寄与する.温度で単独制御するため,後貼りや剥がすこともできる.調光温度は作製時に30℃-60℃の範囲で選べ,極寒-10℃以下から酷暑70℃程度まで耐久性があり,温度繰り返し10000回以上で調光させても劣化しない.この材料は,作りやすく,使いやすく,長持ちする省エネ型のスマートウィンドウに繋がる.

産業技術総合研究所
垣内田洋
-
より長波長方向に吸収をもつ近赤外線吸収エレクトロクロミック材料の開発
近年,バイオイメージング,センサーへの応用,太陽電池の性能向上などを目的として,近赤外光を高効率で吸収する有機色素の研究が盛んに行われている.これまでに,いくつかの研究グループにより芳香族化合物のπ系を拡張して,より長波長の近赤外領域に吸収波長を持つ色素の開発が進められているが,合成経路の複雑化,溶解度の低下が課題となっている.我々は不対電子をもつ有機ラジカルカチオンの吸収挙動に注目した.本発表では(i)容易に合成可能であり,(ii)有機溶媒に良好な溶解度を持ち,(iii)1400 nmを超える極大吸収波長を持つトリフェニルアミンエレクトロクロミック材料について紹介する.

関西大学
矢野将文
-
閉会のあいさつ
【招待講演】
-
22B-1[招待講演]生成AIによるアバターを活用した訓練支援技術
生成AIによるアバターを活用した訓練支援技術(特殊詐欺防止,カスハラ対策)について紹介する.本発表では,生成AIと犯罪心理学の知見を活用することで,訓練者はリアリティーのある詐欺・カスハラシナリオを対話形式で体験する疑似体験機能と体験中の対話や心身状態を基にナラティブを生成しフィードバック機能を開発したので紹介する.

富士通研究所 コンバージングテクノロジー研究所
紺野剛史
-
22B-2[招待講演]放送局における映像自動要約技術の実利用
ショート動画が好まれる時代となり,放送局においても,放送コンテンツの要約動画をソーシャルメディアで配信する機運が高まってきた.そこで我々は,ニュースおよび番組映像の自動要約システムを開発し,番組制作現場での実用化を実現した.重要シーンならではの構図やカメラワークの画像特徴を学習したAIを用いて,実際の番組制作スタッフが編集したものに近い品質の要約映像を自動で生成できる.本システムは,ネット向けコンテンツ制作の迅速化を実現し,放送番組のネット展開を大きく後押しするものである.

NHK放送技術研究所 スマートプロダクション研究部
望月貴裕
【フェロー記念講演】
映像情報メディア学会には,テレビジョンを含む映像情報メディアに関する学術および産業分野の発展・普及・振興あるいは本学会事業の発展に対して,特に貢献が顕著と認められる会員に高い尊敬と深い感謝の意を表するための制度として,フェロー会員の認定制度があります.本企画では,新たにフェローの称号が贈呈されました皆様を講師としてお招きし,映像情報メディア技術の発展に寄与した業績をご講演いただきます.
-
22C-6[フェロー記念講演]光学系および信号処理系と協調したCMOSイメージセンサの高性能・高機能化に関する研究(予稿なし)
私が研究して来た高機能・高性能CMOSイメージセンサとして,コンピュテーショナルフォトグラフィーの考え方に基づく超高速CMOSイメージセンサとその応用について講演する.マルチタップ電荷変調器を利用し,撮像デバイス・光学系・信号処理を融合することで,イメージングシステムの性能を劇的に向上した.
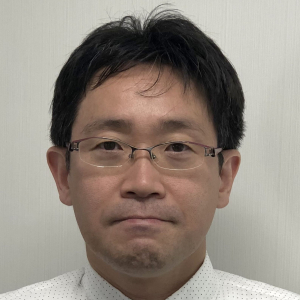
静岡大学
香川景一郞
-
32A-8[フェロー記念講演]テレビのフレームレート変換技術の高度化に向けて(予稿なし)
テレビのフレームレート変換は,国際中継,特に欧州・日米間の中継では,半世紀以上前から必須の技術となっている.高画質映像伝送を維持するためには,動き補正フレーム内挿の高精度化が鍵となる.本講演では,国際TV伝送と同じだけの歴史を持ちながらまだ完璧なアルゴリズムの存在しない,このフレームレート変換技術について紹介する.商用装置化されているアルゴリズムの一例を説明した後,近年需要が高まっているその高速ソフトウェア化について述べる.更に今後の展開として,近年盛んに研究されている深層学習を用いたフレーム内挿方式を概観する.フレームレート変換技術の更なるブレークスルーに期待したい.
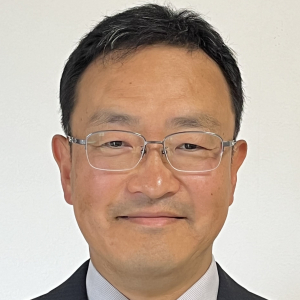
KDDI総合研
川田亮一
-
32C-1[フェロー記念講演]立体映像技術のこれまでとこれから(予稿なし)
今から約20年前に,日本の電機メーカー各社が競って立体テレビを発売した時期がありました.現在は,メタバースやSociety5.0で利用されるVR・AR技術のための立体視ができるヘッドマウントディスプレイやスマートグラスの研究開発が世界中で盛んに行われています.この間の立体表示技術の研究開発の流れについて講演者の研究を中心に振り返るともに,今後の研究開発について展望します.また,映像情報メディア学会における立体メディア技術研究会の活動や役割についても紹介します.

東京農工大
髙木康博