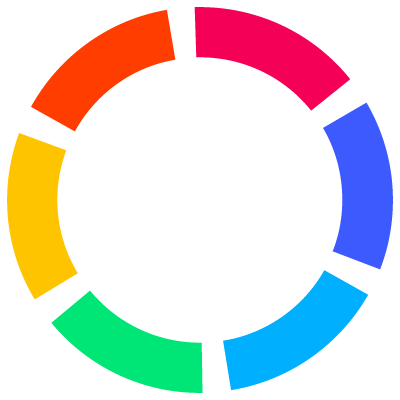シンポジウム,デモ展示など特別イベントに関しての情報を掲載しております。
タイムテーブルに関しましては、こちらのページにて詳細をご覧いただけます。
[企画セッション1]生成AI・SNS時代における情報の信頼性確保と出所・来歴認証技術
企画:大会実行委員会
近年,生成AIの発展やSNSの普及により偽・誤情報の作成・拡散が問題となっている.偽・誤情報は,事実の情報を上回るような強い拡散力を持っており,国際情勢や経済などに大きな影響を与える可能性がある.そのため,情報を発信する企業や個人だけでなく,情報の受け手も情報の信頼性に十分に注意する必要がある.その様な背景のもと,Content Authenticity Initiative(CAI)/Coalition for Content Provenance and Authenticity(C2PA)やOriginator Profile(OP)といった情報の出所・来歴認証技術が注目されている.本企画セッションでは,放送局やメーカーの偽・誤情報への対策からCAI/C2PA,OPの取り組みやその技術についてご講演いただく.
12月24日(火)13:00~14:50
会場A
座長:藤井亜里砂(NHK)
-
開会
-
アドビの生成AIとは? ~ Adobe Fireflyのご紹介と実践例,フェイクニュースを防ぐ取り組みCAI ~
登壇者が変更となっております.

アドビ(株) デジタルメディア 製品戦略部
高橋絵未
-
Webの情報を信じるために ~ オリジネーター・プロファイルの取組 ~
生成AIやSNSによってデジタル空間に偽・誤情報が広く流布し,災害や選挙などにおいても社会や産業の価値を毀損する事案が生じ,より正しく行動することが困難になるだけでなく社会の混乱や分断,不信が生まれている.一方,偽・誤情報は「何が偽・誤情報か」という解釈の余地があるだけでなく,言論の自由の観点から強力な規制が困難だが,その対策が急務となっている.本セッションでは,ウェブコンテンツ,広告流通,第三者機関の情報の信頼性などに寄与するエンドユーザによる発信元の検証を実現するオリジネータープロファイル(OP)の真正性検証技術の開発とグローバルな取組みについて概説する.

慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科/オリジネーター・プロファイル技術研究組合
クロサカ タツヤ
-
NHKにおける偽・誤情報対策の取り組み
インターネット上の情報空間における偽・誤情報の拡散が社会問題となっている.生成AI技術の進展により,誰でも簡単に放送局になりすました高品質な偽動画を作成することが可能であり,放送局が発信する「正しい情報」と,偽情報の見分けが困難な状況となっている.本講演では,偽・誤情報対策に関する国内外の取り組みについて俯瞰するとともに,NHKの制作現場における偽・誤情報対策の取り組みとNHK技研における研究開発動向について述べる.

NHK放送技術研究所 ネットサービス基盤研究部
大竹 剛
-
放送ターゲット広告とそのフェイク動画広告対策に関する技術研究
欧州ではDVB-TA(TS103 752-1),HbbTV-TA(ETSI TS103-736),米国ではATSC3.0 DAI(A/344 A.2)といった放送におけるターゲット広告の技術規格が整備されている.そこで,日本でも放送でのターゲット広告の技術手法を提案する.
また,放送広告は,放送局の考査や放送波の偽装困難性によって安全性が担保されているが,ターゲット広告でオープン市場の広告が提示される場合,フェイク等の不正広告の混入が懸念される.そこで,広告主や考査情報を暗号学的に検証できる仕組みを着想したので提案する.
(株)フジテレビジョン 技術局 技術戦略部
伊藤正史
-
閉会
[企画セッション2]360度映像の最新動向と今後の展望
企画:情報センシング/情報ディスプレイ研究委員会
近年,360度を撮像できるカメラは,コンシューマ向け,業務用向けなど多様な製品が登場しており,映像品質や撮影技術も格段に向上している.また,360度を表示できる表示装置もプロジェクション方式に代わってLEDディスプレイを使用するドーム型シアターが登場し,高輝度・高精細のこれまでにない映像体験を提供するこが可能になっている.本企画では,360度映像における撮像・表示・コンテンツ制作の最新技術を紹介し,没入体験型コンテンツの発展に向けた将来展望について講演いただく.
12月24日(火)14:20~17:40
会場A
座長:林田哲哉(NHK),薄井武順(NHK)
-
開会
-
RICOHにおける360度カメラの歴史と活用事例

(株)リコー 先端技術研究所 HDT研究センター
佐藤裕之
-
360度映像の最前線と未来展望 ~ 没入型コンテンツの可能性 ~
本講演では,VR撮影事業者の視点から360度映像技術の現状と未来展望を考察します.
VRブームの後,市場の変化によりハイエンドカメラの開発は停滞していますが,LEDディスプレイ向け映像,新しいHMDを活用したVR/AR/MRコンテンツ,低遅延映像伝送を用いた遠隔操作など,360度映像の新たな応用が広がっています.
これらの事例を通じて没入型コンテンツの未来展望を探ります.
ジュエ(株) システム構築エンジニアリング部
西條結城
-
休憩
-
プラネタリウムの最新動向
プラネタリウムは星空を再現するだけでなく,デジタル式プラネタリウムの進化によりさまざまなコンテンツを投映することが可能になっている.また,プロジェクターによる投写方式から,LEDモジュールをドーム全面に張り詰めた自発光方式のプラネタリウムドームも実現している.プラネタリウムの上映システムやコンテンツの最新動向を解説します.

コニカミノルタプラネタリウム(株) 技術部開発グループ
黒木 純
-
放送やイベントのための360度映像活用 ~報道利用の観点から~
複数の平面カメラを全方位の放射状に並べ,膨大な時間をかけてスティッチしていた10年前に比べて,小型化し揺れ補正機能が搭載され画質が大幅に向上した最近の360度カメラは,今やプロからアマチュアまでその活用の場を広げている.本稿では放送やイベントに360度カメラを使用してきたNHK映像センターの取り組みを紹介する.

NHK 報道局 映像センター
新井田利之
-
閉会
[企画セッション3]生成AIの現状と今後の展望を語る
企画:大会実行委員会
生成AIの技術革新は目覚ましいスピードで進み,2021年以降多くのLLM(Large Language Models)が発表され,パラメータ規模は指数関数的に増加している.特定の産業や特定の言語に特化した特化型モデルも開発され,金融,医療,教育など,さまざまな産業で生成AIの応用が拡大している.また,画像や音声などを扱うマルチモーダル生成AIや,ロボット技術と組み合わせた新たな応用分野も登場している.
そこで,本企画セッションでは,当分野で活躍されている方々をお招きし,生成AI研究の具体的な取り組み内容と,今後の発展の方向性について講演とパネルディスカッションを行います.
※本セッションは予稿はございません.
12月25日(水)10:00-12:00
会場A
座長:鈴木教洋(日立総合計画研)/映像情報メディア学会 会長
■登壇者
司会:映像情報メディア学会会長 鈴木教洋(日立総合計画研究所 取締役会長)
パネリスト① 花沢 健(NEC データサイエンスラボラトリー 所長)
パネリスト② 穴井宏和(富士通 富士通研究所 プリンシパルリサーチダイレクター)
パネリスト③ 和田真弥(KDDI 経営戦略本部 AI基盤G グループリーダー)
パネリスト④ 柳井孝介(日立製作所 研究開発グループ AIトランスフォーメーション推進プロジェクトリーダ)
■形式:ショートプレゼン(15分程度)+パネルディスカッション
・自己紹介+生成AIの取組みや今後の展望を各人より15分程度ショートプレゼン
・Q1:生成AIによる生産性向上の実態
・Q2:生成AIの課題と対応策
・Q3:学会への期待、若い研究者へのメッセージ
[企画セッション4]2023年度各賞受賞企業による記念講演
企画:大会実行委員会
2023年度に当学会が主宰する各賞を受賞された企業の方々のご協力を得て,記念講演企画を行うこととしました.いま放送の現場で用いられている技術や,次世代の放送を予感できる技術,そして研究の最前線の技術について,それぞれわかりやすく,親しみやすくご紹介いただきます.各企業でどんな研究開発が行われているかについて,企業の特色も垣間見ることができ,大学関係者,学生の皆さんにも貴重な機会となっています.
12月25日(水)13:00-14:50
会場A
座長:森本 聡(フジテレビ)
-
開会
-
<技術振興賞>進歩開発賞(現場運用部門)受賞
バーチャルマスターオペレーターの開発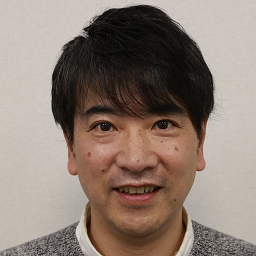
(株)テレビ北海道 技術・DX推進局
高橋康二
-
<技術振興賞>進歩開発賞(研究開発部門)受賞
リアルタイム点群圧縮伝送システムの開発フォトリアルな三次元データ表現形式の一つとして,点群への注目が高まっている.点群は人物などの物体から建造物や都市などの大規模シーンまで多様な対象物を表現できる一方そのデータ量は膨大であり,利活用には圧縮技術が不可欠である.これに対し,MPEGは点群圧縮に特化した世界初の国際標準方式としてV-PCCとG-PCCを2021年と2023年にそれぞれ標準化した.本講演では,筆者らが開発した世界初のV-PCC/G-PCCリアルタイム圧縮伝送システムの概要,およびそれらを用いた実証実験事例について紹介する.

(株)KDDI総合研究所 XR部門 3D空間伝送グループ
海野恭平
-
<技術振興賞>進歩開発賞(研究開発部門)受賞
医師の診断を支援する3次元類似症例画像検索技術の開発と新型コロナウィルス診断への実応用医師の画像診断を支援する3次元類似症例画像検索技術を紹介する.医療における画像診断は,CTやMRIなどで撮影する画像枚数が年々増加する一方,画像診断を行う医師の数は限られているため,1人あたりの画像診断の負担が大きく,医師の画像診断を支援する技術が求められている.
本技術は,臓器内に広がる病変の広がり方に基づいて過去の類似症例を自動検索し,過去の類似症例に紐づく病名などを医師に提示することで,医師の画像診断の負担低減に貢献するものである.本技術の特徴は,画像診断を行う際の医師の見方と画像解析を融合した点にある.
本講演では,3次元類似症例画像検索技術を実現するために開発した要素技術について紹介する.
富士通(株) コンバージングテクノロジー研究所 グリーンイノベーションCPJ
宮崎信浩
-
<技術振興賞>コンテンツ技術賞受賞
新しいビデオペンの開発と多機能化放送で使用される映像信号内に,フリーハンドで軌跡CGを描くことが出来るビデオペンは,これまで専用の放送機材を使用しており,設備導入後の機能追加や改修は困難であった.
そこで,PC等民生機を用いて社内開発することで,従来のビデオペンの機能を大きく超えるシステムを実現できるようになり,これまでは出来なかったCG表現と運用を可能にし,コンテンツの演出の幅を広げた.
具体的には「人物等,移動する物体に追従するCGのリアルタイム表示」「PC画面等に表示される文字情報を自動認識し,テロップへ自動反映」「合成音声技術を使用した機能拡張」「音声分析結果のCG表示」等を実現させた.
日本テレビ放送網(株) 技術統括局 デジタルコンテンツ制作部
岸 楓馬
-
映像情報メディア未来賞受賞
大型カラーアニメーション計算機合成ホログラムの実現コンピュータホログラフィは計算機合成ホログラム(CGH: Computer-generated hologram)と呼ばれるデジタルの干渉縞を使用してリアルな立体映像を再生する技術であり,今後の実用化が期待されている.ここで,大きな画面サイズや広い視域をもつ再生像を実現するためには,原理的に非常に細かい画素ピッチかつ大規模な画素数をもつCGHが必要であり,これに対応する電子デバイスは存在せず動画化は長年の課題であった.著者らは,当該課題を解決するために,前述の画素要件を満たす静止画CGH方式を拡張し,大型カラーアニメーション計算機合成ホログラムを実現した.本講演では,コンピュータホログラフィの原理や動向および著者らの提案技術の詳細について紹介する.

(株)KDDI総合研究所 XR部門 3D空間伝送グループ
野中敬介
-
閉会
[企画セッション5]日・英における地上波デジタル放送をとりまく諸課題
企画:大会実行委員会
12月25日(水)15:30-17:10
会場A
座長:森本 聡(フジテレビ)
-
開会
-
デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 ~ 小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム検討結果 ~
総務省「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の「小規模中継局等のブロードバンド等の代替に関する作業チーム」より「第3次取りまとめ案」が提示された.この案では,IPユニキャスト方式での放送コンテンツ配信は放送の代替手段になり得ると結論付け,制度整備へ前進した.今後の制度化へ向けた課題について解説いただく.

総務省
小林祐介
-
地上波による超高精細度テレビジョン放送等の更なる高画質化を図るために必要な技術的条件
地上波による超高精細度テレビジョン放送等の更なる高画質化を図るために必要な技術的条件について解説いただく.

東京理科大学
伊丹 誠
-
英国における地上波デジタル放送の現状と未来
英国Ofcom(英国情報通信庁)は「Future of TV Distribution(テレビ配信の将来)」を公表した.将来の選択肢として放送波の停止も含まれている.英国における地上波デジタル放送の現状と今後について解説いただく.

マルチメディア振興センター
飯塚留美
-
閉会